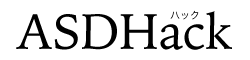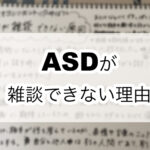この記事は医師の監修を受けておりません
はじめに
この記事は、自閉スペクトラム症(ASD)である私がChatGPTに相談を重ねながら整理した
ASD(ADHD併発)の話し方の特徴と
「定型発達の人」へ伝わりやすくするための工夫をまとめたものです。
ASDの話し方に見られやすい特徴
① 前提が省略されがち
ASDの頭の中では「前提」がはっきりしていても、 会話の流れの中でその前提を言い忘れてしまうことがあります。
その結果、相手からすると突然話題が飛んだように聞こえる、
いわゆる文脈ジャンプが起こりやすくなります。
◯改善方法
- 会話の最初にひとこと前置きを入れる
例:「これは仮の話だけど…」「前提として〇〇なんだけど」 - 自分の中の“当たり前の前提”を一度棚卸しする気持ちで話す
例:
「明日の資料、あれちょっと直したほうがいいと思う。」
↓
「さっきの会議で話していた〇〇の資料だけど、明日の提出前に少し直したほうがいいと思う。」
これだけで、伝わり方が変わります。
② 情報を深掘りしがち
ASDは「縦型の思考」をしやすく、
ひとつのテーマを一気に深く掘り下げて話してしまう傾向があります。
本人は筋道が見えていても、
相手は途中で迷子になりやすい、という形で差が出ます。
◯改善方法
- 話題は一度につき ひとつだけ に絞る
- 相手への質問は 一つのテーマにつき最大2つまで にする
会話がすっきりまとまり、相手もついてきやすくなります。
③ 感情・願望・仮定が混ざりやすい
話している途中で、
事実・推測・感情・仮定が混ざり合うことがあります。
相手が「どのレイヤーの話?」と迷いやすくなる部分です。
◯改善方法
以下の4つを意識して区別してみる
- 事実:〇〇は〇〇である
- 推測:〜かもしれない
- 感情:嬉しい、悲しい、つらい
- 仮定:もし〜だったら
言語化が整うと、相手にも誤解されにくくなり、
自分の思考も軽くなる感覚が得られます。
まとめと注意点
いかがでしたでしょうか。
私たちASDは、定型発達とは感じ方や考え方のリズムが少し違うため、どうしても誤解が生まれやすいところがあります。
今回紹介した工夫はコミュニケーションを円滑にする助けになりますが、同時に注意してほしいのは
これらの方法はASDにとって負荷が高くなりやすいという点です。
すべてを完璧に実践する必要はありません。
大切な場面だけ、できる範囲だけで十分だと思います。
私たちの話し方は、もともとユニークで魅力のある個性でもあります。
誤解を少しでも減らし、心地よくコミュニケーションできるように、
どうか無理のないペースで取り入れてみてくださいね。